>毎日新聞社ニュースサイト >全国学校図書館協議会 >問い合わせ
>学校の先生、書店員さまへ(拡材ダウンロードできます)
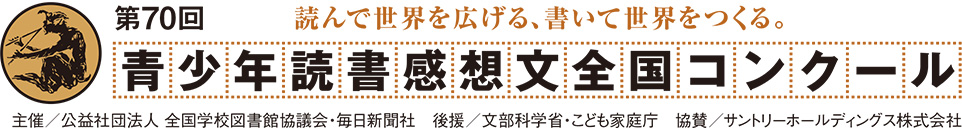
>毎日新聞社ニュースサイト >全国学校図書館協議会 >問い合わせ
>学校の先生、書店員さまへ(拡材ダウンロードできます)
ホーム >課題図書

※すべて税込価格
各課題図書の選定理由は、第71回青少年読書感想文全国コンクール「課題図書」選定委員会の報告をもとにしています。
※『学校図書館』(全国学校図書館協議会)2025年5月号掲載
※レビュー提供元:NetGalley
ライオンのくにのネズミ
![]()
ライオンの学校に転校したネズミのぼく。体の大きさも、言葉も違うライオンと仲良くなんてできっこない!そう思っていたけど…。
【みどころ】
ライオンの学校に転校したネズミのぼく。体の大きさも、言葉も習慣も違うライオンと、仲良くなんてできっこない!そう思っていたけれど…。ネズミの勇気が、世界を変える!「書店員が選ぶ絵本新人賞2024」大賞受賞作。
さかとく み雪 作
中央公論新社
1,760円
転校でライオンの国に来たねずみの不安な気持ちがリスの言葉で救われ、そしてそのリスを助けたいと思った勇気がライオンとも通じ合えるきっかけになります。最後のページで「ああ、そうだったのか」とわかる鮮やかな仕掛けは低学年も楽しめると思います。
親の仕事や戦争、色々な理由で引っ越しをしなくてはならない子どもたちがたくさんいます。言葉の違いや環境の変化は子どもたちにはとても不安です。でも何かをきっかけに少しずつお互いを理解することができれば、お友達になれるかもしれません。お互いを知る勇気のヒントをくれる絵本です。
こんな素敵な本に出会えることができるから、やはり課題図書を設定して、良書に子どもが触れやすくするのは意義深いと感じる、そんなとびきりの一冊。
ぼくのねこポー
![]()
道でひろったねこを、ぼくの家で飼うことにした。だけど、転校生の森くんが、飼っていたねこがいなくなったと話していて……。
【みどころ】
ひろったねこが、転校生の森くんが飼っていたねこかもしれないと気づきます。でも、ねこを手放したくないので森くんのねことは認めたくありません。自分の気持ちと向き合い、大切なことに気づいていくお話です。
岩瀬成子 作
松成真理子 絵
PHP研究所
1,430円
とっさについたうそと、かくしごと。猫への愛着が強まるにつれ、少年のこころに暗い気持ちが広がっていきます。もし自分の大切なものが、別の人にも大切で、てばなさなくちゃいけないとしたら…。そんなときにどう自分の気持ちに向き合えるか、唐突に決断を迫られる主人公に感情移入が止まりません。こんなふうに、欲望と道理のあいだで揺れることって、人生ではけっこうあることに思いますが、この年齢で、しっかりわかってて、えらいなあというのが正直な感想です。
なぜタイトルで『ぼくのねこ』と強調するのか、読み進めるうちに、すごくよくわかります。
猫を拾う、子供がいくつか切望していることの定番のひとつではないかと思う。猫を飼いたいがためについた小さな嘘はそれを隠すためにまたうそでごまかし…自分のしたことでどんどん追い詰められてしまう子どもの心の移ろいが素直に描かれていて、読者となる子どもたちの共感を呼ぶと思った。猫を手放したくない自分の気持ちと、猫を探す友達の気持ち、飼主が恋しいだろう猫の気持ちを比べて何が大切にしたいことか気づくことができた主人公の心の成長が切なくなるが、読んだ子どもたちも一緒に考えることができる、よい結末だと思った。見守っているお母さんの存在も重要。
生き物でも物でも、「名付け」をすると途端に情に切り結んだ繋がりができてしまう。
人に懐いた迷い猫を拾い、ポーと名付けて飼い始めたとおる。
転校生の森くんとことばを交わすうちにある疑念に囚われていく。それが確信に変わるまでの葛藤は痛々しく苦しいが、揺れる心で導き出した答え。
どうするべきかは、ひとつ。ポーの立場に立って考えれば迷いは吹っ切れた。
自分の本心を抑えることで開けるものがあった。
松成真理子さんの絵がすばらしい!
ともだち
![]()
ぼくとエトは大の仲良し! どんな日も「ふたりいっしょ」。ある日、一人の男の子が「仲間に入れてくれる?」と、やってきて…。
【みどころ】
「さんにんいっしょ」になった、ぼくたち。うれしかったり、悲しかったり、言葉にできないような気持ちがうまれることもあるけれど、あせらないで大丈夫。友達との関わりの中で生まれる感情を丁寧に描いた物語。
リンダ・サラ 作
ベンジー・デイヴィス 絵
しらいすみこ 訳
ひさかたチャイルド
1,760円
仲良し2人に新しい友達が加わった時の何とも言えないモヤモヤ感。
幼い頃を思い出した。
子どもの頃の狭い世界って、それだけがすべてだった。
友達がひとり加わることが一大事だった。
この物語に共感できるこどもは多いはず。
かわいいイラストにほっこり、なかなかリアルな物語にドキッとさせられる絵本だった。
まず絵に惹かれました。そしてシンプルなタイトル。
タイトルが直球なように、中身も直球でした。
「ぼくは」親友と段ボール箱2つで遊んでいつも楽しかったのに、新しい子が入ってきて、仲良く遊ぶ2人に嫉妬します。
嫉妬のあまり、自分の段ボールをつぶしてしまう心理も、リアルです。
そんなものを吹き飛ばすように、二人はぼくに、すばらしい新型段ボールをもってきてくれます。
いっしょに遊び、ぼくは3人で遊ぶことの楽しさにやっと気づきます。
子ども時代に誰もが経験したことのある心理を、易しい言葉でわかりやすく表現しています。
最後の3人の後ろ姿の絵が最高でした。
誰とでも仲良く出来る友達を誇らしく思う一方、新しい仲間と直ぐに打ち解けられない(環境が変わることを受け入れられない)自分が、仲間はずれになったような気がして何となく面白くない気持ち。わかります。
私の方が先に仲良くしてたのに。なんて思ったりして。
遊びに誘ってくれて嬉しいのに、意地になって引っ込みがつかなくなってそれっきりなんてことも。
そのままいけば気付くとそれぞれ違う子と遊ぶことが当たり前になってるんですよね。
このお話では、友だちのエトも新しい仲間のシューも「ぼくのために」とっても素敵な提案をしてくれました。
こういう風に思いやりをもって接したいと思う相手が、自分にとっての『ともだち』なんだなと改めて感じました。
ワレワレはアマガエル
![]()
おどろきの生態や体のとくちょうを、アマガエル自身が愛きょうたっぷりに紹介。おたまじゃくしからカエルへの変身も、大迫力!
【みどころ】
「カエル」って聞くと、どんなカエルを思いうかべる? 目がぴょこんと出て、黄緑色の…そう、ワレワレ、アマガエル! 体のとくちょうや、卵からおたまじゃくし、カエルへの大変身。おどろきの生態を楽しくお届けします。
松橋利光 文・写真
アリス館
1,870円
一般的なイメージのカエルって「アマガエル」のことなんだな、と理解したところで、カエルの生態が色々わかりやすく描かれている。これを読んで、カエルを探したくなるよね?さあ、たんぼにでかけてみよう!そんな気持ちにさせられる写真絵本でした。
アマガエルの生態を写真で紹介。松橋利光さんの写真が美しい。
知っているようで細部までは知らないアマガエル。
おもしろい秘密がいっぱいです。舌は伸ばさず体ごとエサに襲いかかる姿は案外野生的。
田んぼの環境がアマガエルの生育に密に関係することを思えば、何やらもやもやするものがこみ上げてきます。
ふみきりペンギン
![]()
ペンギンの声を聞く子。白いヘビのうわさ話を確かめたい子。鏡でライオンに会う子。変わったフクロウを見る子。自分らしさってなんだろう?
【みどころ】
小三のゆうとは、ふみきりの前でペンギンたちにばかにされて落ちこんでいる。「ふつうって、なんだろう?」という問いのこたえを、むりに決めつけず、大げさに気にせず、「自分らしさ」を認めていく、やさしい物語。
おくはらゆめ 作・絵
あかね書房
1,430円
本当は小学校中学年が対象らしいが、大人の私も心から楽しめた1冊。
読みながら、自分が一気に小学生に戻ったような気持ちになった。
ちょっとしたことでけんかして、悲しくなって、でも、すぐに仲良くなれて。
へびやライオンの友だちだって、たくさんいたよね。
こんなに楽しい本、自分が小学生の頃に出会いたかったなぁ。
「らしさ」とか「個性」がテーマなのだと思うのです。
でもそのようなことよりも、心のままに楽しく読んで欲しい本です。
同じ小学校に通う児童が1話ずつ主人公になっている物語です。
左ききのゆうと。近所のへび公園の都市伝説を信じるるり。旧校舎のトイレでふしぎな体験をしたななこ…
この作品の街では人間と不思議な生きものが共存しているような、していないような。
そして楽しく「ふつうって何?」と思ってくれたら気持ちが軽くなる子が増えると思います。
イラストもとても楽しく、ほんわか優しい気持ちになれました。
バラクラバ・ボーイ
![]()
バラクラバ帽をかぶった転入生のトミーがやってきた。なぜトミーは帽子をかぶってるの? あの帽子の下には何がかくされている?
【みどころ】
バラクラバ・ボーイがやってきて、たいくつな毎日は一変! 個性豊かな仲間たちが巻き起こす、笑いと友情の青春物語。"みんなと違う"を受け入れたとき、予想もしなかった驚きと感動の結末が待っています!
ジェニー・ロブソン 作
もりうちすみこ 訳
黒須高嶺 絵
文研出版
1,540円
課題図書を低学年~中学年まで読み切ったけれど、その中で今のところこれが1番読者に届いてほしい本だと思いました。
決して「お行儀の」いい本ではないけれど、勉強や教育の香りが一切しないリアルな子ども目線が逆に押しつけがましくなくて、普段本を読まない子にこそ「面白い!」と思ってもらえると思います。
転校生の「ある1点」だけに着目して、1冊丸々ぐいぐい読ませるストーリーテリングも素晴らしいです。日常の中にこそ面白さがあるのだなと。
どこの学校のクラスにもいそうな、おふざけお笑いコンビや、まじめかしこい子が中心になって、バラクラバ帽をかぶったままで顔を見せない転校生の秘密を明かそうと、次から次へと、ちょっかいを出すなかで、クラスがまとまって行く。バラクラバ帽から、子どもたちが想像を広げる様子が、イラストもていねいに盛りこまれ、楽しい。転校生の秘密を探るなかで、クラスの友だちの新しい面も明かされ、子ども一人一人のユニークさが愛おしい。こんなクラスの仲間になりたいと思わせる結末もすてきだ。
たった2℃で…:地球の気温上昇がもたらす環境災害
![]()
気温が2℃上がると、地球でくらす生き物みんなの命があぶない!植物も動物も、あなたも、わたしも。いっしょに考えよう!
【みどころ】
気温が2℃上がったらどうなると思う?人間も、植物も、陸や海の動物たちも…地球でくらす生き物みんなの命があぶなくなるんだ。もうこれ以上、地球の気温をあげないために、わたしたちにできることは?
キム・ファン 文
チョン・ジンギョン 絵
童心社
1,980円
地球温暖化をとてもわかりやすく教えてくれる1冊。
ウミガメの産卵で温度によって性別が変わるなんて知らなかった。
動物に与える影響が描かれているので、想像もしやすく、身近に捉えることもできると思う。
小学生にもわかりやすいはず。
たった2℃、されど2℃だ…
地球温暖化が、自分たち人間を含め、生き物全体に、どんなにたいへん深刻な事態をおよぼしているか、子どもにもわかりやすく描かれている。温暖化を病気と伝えていることに、複雑な気持ちになる。この本を読んで、この病気の原因を、さらに探究してもらいたいが、人間自身に原因があることを知り、子どもたちはどうにかしようと考えてくれるだろうか。
地球の気温上昇によって生き物(動物も植物も)が被る悪影響を実にわかりやすく解説している。
2℃気温が上がれば、今の地球の生き物たちは絶滅の方向に向かわざるを得ない。気温に適応できないからだ。
危機感しかない!環境が破壊されていく。
食い止めることができるのは人間だけなのに!
ねえねえ、なに見てる?
![]()
同じ場にいても、見ているもの、その見え方は全く違う。食卓を囲む家族の異なる世界を描く、多様性と共感について知る絵本。
【みどころ】
科学者のママ、ゲーム好きのパパ、音楽家のおじさん…同じ場にいても、見ているもの、その見え方は全く違う。食卓を囲む家族の異なる世界を描く、多様性と共感について知るユニークな絵本。
ビクター・ベルモント 絵と文
金原瑞人 訳
河出書房新社
1,793円
物も捉え方、見え方、感じ方はみんな違う。だからこそ「違い」を知ることが、多様性や共感とは何かを知る最初の一歩なんだと感じました。
トーマスを通した見え方は驚きと共感でいっぱい!
人それぞれで良いんだという安心感と、自分のことも他者のことも、きちんと知ることの大切さが伝わります。
ユニークでポップなイラストが私は大好きです!
スペインの絵本ですが、世界標準!絵の隅々まで確認しながら読んでいくと楽しいです。
色覚障がいのトーマスは自分が見ている世界とみんなが見ている世界が違うことを知っています。
そこで食卓を囲むみんなはそれぞれがどう見えているのか想像します。
体格の違いだけではなく「科学者のママの見え方」「むかしのゲームが好きなパパの見え方」などとっても面白い。それぞれの「色メガネ」は人間だけではなくなっていきます。
どこから読んでも楽しい出会えて良かった1冊です。
ぼくの色、見つけた!
![]()
―ぼくは生まれつき、みんなと同じようには色が見えていないらしい。悩みを持つすべての子に読んでほしい、心が軽くなる物語。
【みどころ】
「色覚障がい」を隠して生活する信太朗。赤いトマトや焼けた肉が見分けられず、困ることもたくさん。しかし、自分の見え方に寄り添って考えてくれる担任の先生に出会い、「自分の世界の見え方の特別さ」に気づいていく。
志津栄子 作
末山りん 絵
講談社
1,650円
読んで良かった!
子どもにも大人にも読んでほしい。特に先生に当事者の子どもの抱える困難や、どんな思いで学校で日々を過ごしているのかを想像して頂きたい。
自分の「色覚障がい」が周囲に分からないように、いつも周りの様子を気にして窺っている信太朗。
ただ少年の悩みや葛藤を描いているだけじゃなく、家族や先生・同級生との関わり、そのどれもが丁寧に描かれていました。
特に先生の然り気ない気遣いやサポートのあり方、押し付けがましくない距離感で自分の方から歩みよる姿が素晴らしいなと感じました。
男の子のこれまで見ていた世界が変わる様子。楽しくって仕方がないのが伝わってきて、私まで嬉しくなりました。
主人公の男の子だけじゃなく、家族一人一人がみんな楽しく清々しい気持ちになれるのがとても良かった!
昔サービス業で勤務していた頃、色覚障がいの後輩がいました。
ある朝、電気をつけていたら、「自分は色盲だから赤と緑の色が判らなくて、電気のスイッチを見てもついてるか分からないんです」と教えてくれました。
もしかしたら、いつも人任せなことに引け目やもどかしさを感じていたのかもしれない。
全く気づかず、そういうこともあるんだと、その時初めて身近なこととして感じたのを覚えています。
この作品をきっかけに、何かが変わる人がいるかもしれない。
とても爽快な読後感で、色覚障害の少年の成長物語でもあり家族物語でもありました。
児童書ですが、読み応えがありおもしろかったです。
色覚障害をもつ小学生信太朗くんが悩みながらも、自分だけの素敵な世界をみつける物語です。
小中学生にとって、人とちがうことは、もはや「恐ろしい」ことの一つといってもいいほどです。
大人になるにつれて、人との違いは「自分らしさ」「個性」と呼ばれ、自分の武器となり、貴重なものになっていくのですが……。
まだまだ人との違いが恐ろしいと感じている子どもたち(大人も)にとって、どうにもならない悩みに、ハラハラドキドキしたり、イライラしたり、泣きたくなったりと揺れ動く信太朗くんの気持ちは「うんうん、わかる」とつよく共感できるものでした。
そして、悩める信太朗くんが気づいた自分だけの世界の美しさは、私も自分だけの世界をいつでもみつけていこうと、大人の私にも勇気をあたえてくれるほど素敵なものでした。
色覚障がいという言葉は聞いたことがあれど、その方たちには、どんな風に世界が見えているのかはよく知らなかったので、この本を通じて知ることができてよかったです。
トマトが熟しているかどうかや、肉が焼けたかどうか…
赤が認識しにくい、といわれるより、よっぽど分かりやすかったです。
悪いことをしているわけじゃないのに、お母さんの顔色をついうかがってしまったり、心配されるほど疎ましく思ってしまう信太朗。
そんな彼に共感し、どんどん話に引き込まれました。
信太朗と同年代の読者なら、なお、共感できると思います。
障がいがテーマなのに重すぎることなく、爽やかな気持ちで読み終えました。
これを読んでくれた児童たちには、授業にも出てくる、ユニバーサルデザインやバリアフリーにまで、意識を持っていってくれるといいな。
森に帰らなかったカラス
![]()
少年ミックが手当てをしたカラスのヒナは、ケガが治ったあとも家に戻ってくるように…。少年とカラスのふれあいの物語。
【みどころ】
少年と動物とのふれあいをえがく、心に残る物語です。ロンドン動物園の元主任飼育員の少年時代の実話に基づいています。舞台は1950年代後半。父親の兵士時代の心の傷にもふれ、命についても深く考えさせられるお話です。
ジーン・ウィリス 作
山﨑美紀 訳
徳間書店
1,760円
ミックが助けたニシコクマルガラス「ジャック」を育てるなかで、ミックの心が成長していく。
命について、ミック自身がどのように思っているのか。
子どもらしく「母鴨」の命への気持ち。
「ジャック」や他の動物への気持ち。
そして、父への気持ち。
私が注目したのは、ハーベイさんのお母さんに対するミックの考えの変化。
この短い物語のなかで、ミックが命に対してどう思いまた、自分以外の立場への考えが「自分軸」から抜け出して客観性を持つところまで描き出されているところが素晴らしいと感じる。
また、家族が(父親が)戦争にどうかかわっていたのかを知ることでミックの気持ちが変化するところは圧巻だ。
小学校高学年むきということだが、中高生も読めるし、大人も一緒に読んでほしい。
少年ミック、その家族や友人、嵐で傷ついたニシコクマルガラスの実話に基づいた物語。人間と動物との間にエピソードは多く、一つとして同じものはなく、各々の作品で愛が育まれている。特に鳥は知能が高く本能を超え、憧れの存在である。交わせない言葉が結びつき、心通わせることで少年たちを豊かにしていく。生きる世界は違うけど、ずっと一緒にいたい、その気持ちは永遠。本作には父親の戦争体験も記されている。戦後間もない時期は深い傷が癒えることなく蓋をしておくしかない状況。温かさと痛々しさ、表裏を感じ取れる印象的な作品。
戦争の影が残る時代背景。
ミックの家族や周囲の人々がジャックを受け入れていく様子が温かく、読んでいてほっとする場面ばかりでした。
特に、ジャックが列車と競うように飛ぶ場面は、胸が熱くなりました。動物との触れ合いを通じて、人の心の奥にある優しさや痛みが描かれていて、読後には静かな余韻が残ります。
父親の戦争にまつわる過去とジャックというカラスの運命が、対比的に描かれていていろいろなことを考えさせられました。
マナティーがいた夏
![]()
11歳の夏休み、ピーターはすべてうまくやれるはずだった。けがしたマナティーも、救えるはず。変化に向き合う勇気をくれる成長物語。
【みどころ】
物語は、マナティーが泳ぐ美しい場面から始まる。主人公にとってマナティーは、祖父の思い出で、親友との大発見で、心を落ちつかせてくれる存在。その保護のためにさまざまな人と関わり、奮闘する姿が胸を打つ感動作。
エヴァン・グリフィス 作
多賀谷正子 訳
ほるぷ出版
1,760円
『マナティーがいた夏』は、夏が終われば中学生になる少年の、想像もつかなかった出来事がぞくぞくと襲う怒濤の夏休み物語です。
楽しい夏のはずだったのに。
友達のこと、家族のこと、ご近所さんのこと、マナティーのこと……。
「上手くいかないことばかりのときってあるんだよね~」「それが夏休みとぶつかるなんて……。」とピーターに同情してしまった大人の私。
ピーターがどうやってこの危機をひとつひとつ乗り越えていくのか?ハラハラでした。
大きくなるにつれて、自分が抱える問題も大きくなっていく。ピーターのようにいくつもの問題が重なることもある。
大人なるって、乗り越えられるだろうか?と思うほどの、大きな高い壁にぶつかること。
そんなときには、「力をかしてください」と言える勇気をもつことが必要で、大切になってくる。
だけどただ「力をかしてください」と言うだけでは、だれも力をかしてくれない。
じゃあ、どうすればいいのだろうか?
ピーターをみればわかる。
ピーターは、問題に対して、とことん悩み、まずは自分でどうにかしようとがんばっていた。
そして、それまでのピーターは、親友を純粋に信じていたし、おじいちゃんを大好きだったし、ママとも信頼関係があったし、自然に生きる生き物を愛していた。
つまり、その問題にどれだけきちんと自分なりに向き合っているか、そして、今までの行いや態度、気持ちがあったからこそ、周りのみんなが「力をかしてくれる」のだ。
言葉でただ「力をかしてください」と言うのは簡単だ。
でも本気で「力をかしてください」と言えるのは、自分の本気度や、今までの自分の態度や気持ちに自信がなければ言えない、勇気のある尊い一言だ。
この夏に、「力をかしてください」と言えるようになるほど、ピーターは大人になった。
「力をかしてください」というのは弱い証しではなく、それまでの自分に自信がもてるから言える勇気ある一言。
そして今までの自分が今の自分を助けてくれることを、ピーターは大人の私にも教えてくれた。
夏の空気を感じながら、心がじんわり温かくなる物語でした。
ピーターのひと夏の冒険は、ただの成長物語ではなく、友情や家族の絆、そして生き物への優しさがぎゅっと詰まっています。
特に、マナティーとの出会いがピーターの世界を広げていく様子が印象的でした。
読んでいるうちに、ピーターの気持ちに寄り添いながら、自分の夏の思い出もふっとよみがえってくるような感覚がありました。
文章は読みやすく、情景が鮮やかに浮かぶので、まるでピーターと一緒にカヌーを漕いでいるような気分になります。
静かだけれど力強いメッセージが込められた一冊で、読んだ後には、なんだか優しい気持ちになれる作品でした。
高齢者への戸惑い、友情の試練、そして、母親としての矜恃! いいお話でした。
ほるぷ出版のこの本のHPは、とっても素敵でした。子どもたちにもすすめます!
小学校最後の夏。「生き物」大好きなピーターは親友のトミーと運河で大けがをしたマナティーを見つける。
他にも色々と問題が起こって…
自慢のおじいちゃんの認知症。シングルマザーとして頑張るお母さん。お金があるからといばるご近所のおじいさん。親友トミーとの関係。そしてゾーイと名付けたマナティー。
子どもから大人に向かう時に、自分の周囲で次々と表面化していく問題を通してピーターは成長していきます。児童だけではなく、大人にも読んで欲しい本です。
とびたて!みんなのドラゴン:難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険
![]()
難病ALSと闘う先生と小学生たちが合唱全国大会を目指す! 人前で話せない内気なマナミや仲間たちの冒険と成長を描く感動実話。
【みどころ】
内気な女の子マナミが出会ったのは、難病ALSをわずらう先生だった。新米顧問の先生と合唱部の子どもたちはそれぞれの想いをかかえ、合唱コンクールの全国大会金賞をめざす。1年間の冒険を描いたノンフィクション。
オザワ部長 著
岩崎書店
1,650円
実際の出来事が、マナミの気持ちや変化と共に描かれている。決して才能のある集まりではなく、やりたい意欲を持った子達が集まる合唱部。
わたしも同じ境遇で、公立校の吹奏楽部でありながら、全員参加の集まりで全国へ行った経験がある。臨場感を思いだし手に汗にぎった。
エピローグには全ての子どもたちへ伝えたい言葉がつまっていた。ぜひ読んでもらいたい。
非常に面白く読みました。
ノンフィクションですが、書き手の方が各登場人物におきたことをドラマティックに描いているので、物語として読みやすいです
子どもたちは子どもに感情移入できるし、大人も、大人にかかわる大人として先生目線で興味深く読むことができると思います。
小学校の合唱部が全国大会を目指します。とはいえ新しい顧問の先生は専門外だし実はALS。部員も多くはない。6年生からの新入りもいる。
逆境の中で彼らはどのように最高の歌を目指すのか。
顧問の役目は技術の指導ではなく、子どもたちが力を発揮できる環境を整えること。
ビジョンを持たせたり、主体性を持たせたり。部がうまくいかないときにこそどうするか、に魅せられました。
『とびたて!みんなのドラゴン:
難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険』は、ノンフィクション小説で涙なしでは読めない本でした。
涙の理由は、先生が難病だからではありません。
児童たちが先生を慕い信じて、自分たちの合唱をつくりあげるために、それぞれが必死になり、話し合い、励ましあい、互いに尊敬しあい、信じあって、みんなが声を、心をひとつにしていく姿に泣けるのです。
先生も児童の、みんなで歌いたい!歌っていたい!という想いが、本のなかからあふれでてくる臨場感もあります。
そして歌声までもが聞こえてくるような……。
本を読みながら、いろんな素敵な奇跡を目の当たりにしました!
竹永先生マジックというのでしょうか。
先生だから、大人だからとか関係なく、大切な人に自分の気持ち、自分の弱さをきちんと伝える勇気をもっているのが竹永先生の最大の魅力です。
そんな先生の魅力が、児童に先生自身に魔法をかけて、たくさんの奇跡が起きたんだと思います。
わたしは食べるのが下手
![]()
会食恐怖症と摂食障害。ふたりの少女がたどり着いた正しい“食”との向き合い方とは。わたしたちが望む給食って、どんなだろう?
【みどころ】
食にまつわる悩みを抱えたふたりの中学生が、背中を押してくれる先生や、様々な環境の友だちとのかかわりを通して、少しずつ悩みと向き合っていく様子が描かれています。食べることの大切さを教えてくれる物語です。
天川栄人 作
小峰書店
1,760円
「わたしたちが望む給食」を考える過程が丁寧に描かれていました。他者になかなか理解されない悲しみや苦しみをもつのは自分だけだと10代は思いがちですが、そうではないことに気づけたのがよかったです。食べることに様々なむずかしさを感じる生徒の声だけでなく、給食がセーフティネットとなる生徒や給食を楽しみにしている生徒の声もちゃんと書かれていて、「無視されてもいい声はないこと」を生徒には読んで感じてほしいです。
面白かった!
食べるという、生物が生きていく上で必要不可欠なこと、かつ、ほとんどの人がなんの疑問も感じずに無意識に行なっていることを取り上げてくれてありがとう、という気持ちです。この作品を読みながら、「食べるのが下手」な葵や咲子と同じように、自分自身も「食べるのが下手」なのだと気づきました。毎日甘いものを食べずにはいられない、これもまた摂食障害なのではないのかと。子どもたちがこの本を読んで、食べるということについて、改めて考えてくれたらいいなと思います。
大好きな作品の1つになりました。
子どもの頃は完食指導だった給食に苦手意識があったけど、大人になってからは給食のありがたさを毎日感じています。
実際に会食恐怖症も摂食障害も学校にいます。大人がどんな関わりをしたら良いか少し分かった気がします。
また、安くて栄養満点の給食を提供する栄養士さんの苦労も垣間見れたので、子どもたちが読んだ時も何かしら感じてくれると嬉しいです。
中学校の課題図書になっていますが小学校の蔵書にも入れたいです。
スラムに水は流れない
![]()
インドのスラムは水の供給が極端に悪かった。少女ミンニは水関連の事件や母が倒れるなどの試練の中、健気に生きぬいていく。
【みどころ】
スラムはムンバイの人口の40%が住んでいるが水は5%しか供給されていなかった。兄が身をかくし残された少女ミンニは、母が倒れるなど次々とふりかかる試練にまけず知恵を働かせ難題をのりこえていく。
ヴァルシャ・バジャージ 著
村上利佳 訳
あすなろ書房
1,760円
水不足に苦しむムンバイのスラムを舞台にした物語。
主人公のミンニは、家族とともに厳しい環境の中で生きています。
水を得ることがどれほど大変か、そしてそれが生活にどれほど影響を与えるかが、リアルに描かれています。
こんな現実があるなんて、全く知りませんでした。
この作品の魅力は、ミンニの成長と希望を描いている点ですね。
困難な状況でも前を向き、周囲の人々と助け合いながら進んでいく姿は、勇気を与えます。
また、インドの社会問題にも触れられており、普段意識しない世界の現実を知るきっかけになります。
文章は読みやすく、物語の展開もスムーズで、子どもから大人まで楽しめます。
さすが課題図書。隙のない作品でした。
蛇口をひねれば飲める水が出てくる日本にいると、毎朝バケツで水を汲みに行く生活なんて、なかなか想像できませんよね。
しかも、汲んできた水は沸かさなければ飲めない。私たちが当たり前のように使っている水が、ムンバイでは簡単には手に入らないのです。
ムンバイのスラムに住むミンニには、次々と問題や災いが降りかかります。仲の良い兄と離れて暮らさなければならなくなり、母親は体調を崩してしまいます。
そのため、ミンニは毎日、母がしていた水汲みや家事を引き継ぎ、さらに母の代わりに働きに出ることになります。そうして初めて、母親が日々どれほど大変なことをしていたのかを知るのです。
けれど、ミンニはまだ学生です。だからこそ、そんな大変な生活を送りながらの学校生活は、母親不在の今、ますます過酷なものとなっていきます。
「スラム」や「カースト」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんな生活がそこにあるのか、想像するのは難しいものです。
ミンニの視点から物語を読むと、水がどれほど貴重なものか、痛いほど伝わってきます。そして、彼女がノートに綴る言葉は、心の奥底からの叫びのようでもあります。
ミンニの聡明さが、この物語を思わぬ方向へと導いていくのも印象的でした。
差別は良くない、そんな単純な言葉では語れないリアルな事情がこの物語には詰まっています。
特に印象的だったのは、お父さんの言葉。
「災いは、こっちが呼ぶからやってくる。いったん来たら、お茶を飲んで、飯を食って、ゆっくりしていくぞ」
この一言には、スラムに生きる人々の現実と、生き抜いていくための強さを感じました。
この物語の核となるのは“水”。その水をめぐって、さまざまな災いが次々と起こります。人は水がなければ生きていけない。
だからこそ、この物語は、私たちの普段の生活を見直すきっかけになるかもしれません。
「スラムに水は流れない」を読んで「逞しい」と感じた
この一文から想像する何倍ものエネルギーをはらむ
出勤前に読みはじめ、ひと仕事をおえた夜に読了
しまった 早朝に読みおえたい物語だった
それほどに眼前に見たこともない拡がり
わたしはなんてラッキーなんだろう
水、水、水。なんでもかんでも水だ
蛇口から水はでない 學校よりも水が出るかでないかが大事
水がないことが人間をぎすぎすさせ家族の有り様を変え災いを招く
昔々の物語ではない
パソコンもアプリもある時代 ただし場所がインドムンバイのスラムだった
豊か ってなんだろう
毎日煮沸消毒せずに飲める水が豊潤にあったなら
よその人の手のなかにあったじぶんの将来を変えてゆく
働く人の手を持つ12歳の少女を突き動かしたろうか
周囲は顧みず支えることを申し入れたろうか
~一つ一つ乗り越えていきましょう。1日1日が小さな勝利。それをお祝いしましょう~
と言いながら
少女の観察眼の冴えっぷりも、見もの
それを肯定的に言語化する翻訳者の技能も、読み応えに加味
~<いつか>は<今日>じゃないんだ~
次のドアを開けるときがきた
鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者
![]()
「知の巨人」ともいわれた夫の鳥居龍蔵や家族とともに、人類学の研究に取り組み、調査を進めた鳥居きみ子の生き様を描きます。
【みどころ】
調査にくわわる子どもたちを母として気遣い、励まし、また研究者としてやるべき調査を進めました。「家族で調査・研究する」という形で、女性の活躍が厳しい時代を生き抜いた、鳥居きみ子の生涯をお伝えします。
竹内紘子 著
くもん出版
1,540円
鳥居きみ子の生き方は、まるで時代を駆け抜ける風のよう。
明治の女性が家庭に収まるのが当たり前だった時代に、彼女はフィールドワークへと飛び出した。
モンゴルの広大な草原を歩き、現地の人々と語り合い、文化を記録する。
その姿は、ただ夫を支える存在ではなく、研究者としての確かな足跡を刻んでいる。
読んでいると、「女性だから」と諦める必要なんてないんだ、と勇気が湧いてくる。
きみ子の挑戦は、今を生きる私たちにも響く。夢を追いかけること、家族とともに歩むこと、そのどちらも選べるのだと教えてくれる。
鳥居きみ子の夫、鳥居龍蔵は人類学の発展のために尽力した世界的な学者として知られ、明治から昭和にかけてモンゴルや中国で遺跡調査を行いました。きみ子も民族学的な調査研究を行い、龍蔵の片腕として数々の実績を残します。学者としての鳥居きみ子に焦点を当てた初めての本です。画期的であるばかりでなく、世界各地で戦争が行われる今、最も読まれるべき本だと強く思いました。
遺跡は現地で調査するしかありません。けれども戦争によって調査を中断せざるを得なくなるなど、思うに任せぬ状況が生じ、読んでいてもどかしく感じました。戦争さえなければ。今、この瞬間にも、そう思っている人がたくさんいるはずです。
二人のように誰に対しても相手を尊重し、敬意を持って接することは非常に重要ですが、なかなかできることではありません。龍蔵はきみ子を一人の人間として尊重し、妻、母ではなくきみ子自身として生きることを促します。理想的な関係と言えますが、二人が生きた時代にあってはもちろん、現代日本でも珍しいことではないでしょうか。未来の夫婦のあり方を示唆しているように感じました。
読み終えて、平和な世界を願わずにはいられません。ぜひ多くの人に読んでほしいと思います。
銀河の図書室
![]()
宮沢賢治の言葉を残して、突然学校から消えてしまった先輩。その謎を追う高校生たちの今を瑞々しく描く、傑作青春小説。
【みどころ】
高校の図書室で宮沢賢治を研究する弱小同好会・イーハトー部。部長だった風見先輩はなぜ突然消えてしまったのか――先輩が残した「ほんとうの幸いは、遠い」というメッセージに秘められた謎が、深く心に響きます。
名取佐和子 著
実業之日本社
1,870円
なんて尊い青春を見せてもらえたのだろう。
読み終えて、あ~良かったと声に出るような、ありがとうと言いたいような、胸が一杯になる気持ち。
それぞれが自分のこと、言動、行動について深く考えている姿を応援する気持ちで見守った。
ビブリオバトルで紹介された本や、賢治さんの未読の本も読みたくなった。出会えて良かったと思える1冊だった。
これから訪れる、長いようで短い夏の始まりとリンクして、この物語の駆け抜ける青春を感じました。
人生の中ですべてはたった一瞬のこと、でも忘れられない出来事、そういったターニングポイントが人にはあると思います。
《ほんとうの幸いは、遠い》という言葉を残して姿を消した先輩の背中を追って、宮沢賢治の残した言葉を追っていくうえで、自分や友人、先輩の心に向き合う時間があります。その時間、自分が何者かになろうともがいている苦しみも、諦めないことも、これからの人生の岐路において大切な出来事だったのだと感じます。
図書のレファレンスのように、答えを教えるのではなく、答えにたどり着けるよう力を貸す大人たちの姿も印象的でした。
そうか・・こうやって、続いていくのかと思った。
すぐれた作品というのは、こうやって何十年もたった世界で、読まれ続けて、人の生き方に影響を与えるのだ。
高校生たちの迷いながら進むひたむきな姿に、宮沢賢治が与えた大きな影響を思ってため息が出た。
でも・・とハッとした。
この高校生たちがあまりにも生き生きとしていてつい忘れていた。
この子たちも、作品の中で生きている人たちなのだ。
物語の中の物語・・幾重にも折り重ねられた箱の中をのぞいたような気がした。
夜の日記
![]()
イギリスからの独立とともに、分かれてしまった祖国。少女と家族は安全を求めて、長い旅に出た。ニューベリー賞オナー賞受賞作!
【みどころ】
ちがう宗教を信じる者たちが、互いを憎みあい、傷つけあっていく。安全を求め旅に出た家族。自分の思いをことばにできない少女は亡き母にあてて、揺れる心を日記につづる。『アンネの日記』をほうふつとさせる傑作。
ヴィーラ・ヒラナンダニ 著
山田 文 訳
金原瑞人 選
作品社
2,420円
なんと、読んだその日に、インドとパキスタンの一触即発状態がアメリカの口利きで停戦になったというニュースがとびこんできました。
まだまだ不穏さはありますが、ほっと胸をなで下ろしました。
この物語は、1947年、インドとパキスタンの分離独立という歴史の大きな波に飲み込まれた少女ニーシャーの視点から、家族の絆やアイデンティティの揺らぎが描かれていました。宗教っていったいなんなのでしょうねえ。
亡き母に宛てた日記という形で綴られる言葉は、時に切なく、時に力強く、読むほどに胸に響きました。
宗教や国境によって人々が引き裂かれる理不尽さの中で、ニーシャーは自分の居場所を探し続けます。
彼女の静かな強さと、料理を通じて紡がれる人とのつながりがとても印象的でした。
(料理についてもっと知りたかったかなあ……)
静かだけれど、深く響く一冊でした。
金原瑞人先生が選者なのですね。さすが、まちがいない物語をもってきてくれます。
そして、みごとに訳者がこたえてくださっていて、みごとな作品となっています。タイトルもいいですね!
想像できるだろうか
1日16キロを歩き通した挙句
保持している食料がバックの中のピスタチオ3粒
そして知らない人から首にナイフを突きつけられおどされる
1947年イギリス支配から独立するインドを日記から読み識る
家族がいること 暖かい毛布にくるまること 作りたての料理を食べること シャワーがあること
それのどれもが奇跡にしか思えないほど 追いつめられていく
知り得ないところで聞いてはいけないことが群発している
恐怖や不安にあがらう術を知らない
何故なら日記の書き手は12歳の少女だから
命をかける
その言葉の引用に恐れ戦く
~ママの話しかける声が聞こえる「ニーシャー あともう1歩だけ」~
覚悟以上の力がもたらされる 窮極の物語
1947年のインドとパキスタンのイギリスから分離独立。これまで仲良くやって来たのにイギリスから独立することで何故宗教が違うだけで住むところをおわれ、暴力にさらされるのか。12歳の少女がその歴史の波にのまれる話だ。そしてひどい話。でも実際にこんな事が起こっていたし、今も起こっている。やるせなくて苦しい。
「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて
![]()
もし、親の耳が聴こえたら――なんて、想像もつかなかった。言葉やコミュニケーションの本質、「善意による差別」って何だろう?
【みどころ】
聴こえない/聴こえにくい親のもとで育つ聴こえる子ども=「コーダ」。ろう者と聴者のはざまで生きる経験を通じ、言語やコミュニケーションの大切さ、自分と異なる人の立場を想像する難しさを知るノンフィクション。
五十嵐 大 著
紀伊國屋書店
1,760円
「コーダ」という言葉は聞いたことがあった。
聴覚障がいのある両親のもとに生まれた聴者を指す言葉だということも理解していた。
言葉としては知っていても、それが実際にどういうことなのか、全くといっていいほど知識がなかった。
本書は、「こういう人がいますよ」「こういう風に暮らしていますよ」「差別はいけませんよ」「お互いに理解し合いましょうね」というような、単純なことが書かれているわけではない。
コーダである著者が、どういう環境の元、どういう気持ちで、どうやって今まで暮らしてきたのか。
きれいごとだけではない。
一人の人間が、理解されない苦しみ。
『コーダ』というラベルで一括りにされることで得た安心感と違和感。
そう言った本音や葛藤が赤裸々に語られている。
同じ「コーダ」であっても、人によって、それぞれ考え方が違う。
当たり前のことだ。
外国で、「日本人だから魚が好きだろう」と魚を振舞われても、魚が嫌いな日本人だっている。
それが、マジョリティの立場からは、理解が及ばない。
そういった、マイノリティーの置かれた状況、日々感じる不平等の世界を、著者が明確に言葉に表してくれた。
本書を当事者以外の人たちが読めば、知らない世界を知り、聴覚障がい者やコーダ、その他のマイノリティーに配慮しようと気持ちになると思う。
そういう意味では、もちろん良書だが、それ以上に、当事者たちが、自分たちの抱える、言い表せない気持ちを語化してくれたということに喜びや安ど感を覚えるのではないかと思う。
聴こえない親を持つ「コーダ」としての経験を綴った作品。
著者は、手話を母語としながらも、聴者の世界にも属するという独特な立場にあり、日常の中で感じる葛藤や、社会との関わり方について深く考えさせられます。
手話と日本語の違い、コーダとしてのアイデンティティ、そしてマイノリティとして生きることの難しさが描かれていて、己の無知にあ然とします。
文章は読みやすく、著者の率直な語り口が心に響きます。コーダやろう者の世界について知るきっかけとなるだけでなく、社会の中で「理解すること」の大切さを改めて考えさせられる一冊です。
多様な視点を持つことの重要性を感じる、貴重な作品でした。